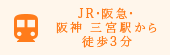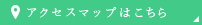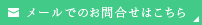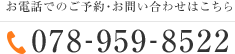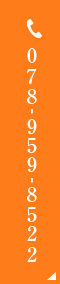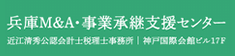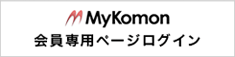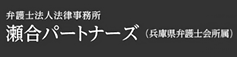税務調査で私名義の預金も相続税が課税されると指摘されました。なぜ???
事例
私の夫が2年前に亡くなり、相続税の申告を済ませたのですが
先日税務調査があって、私名義の預金8000万円にも相続税が課税されると
指摘されて驚いています。
私の夫名義の財産は、自宅と預金が2000万円でした。
たまたま路線価が高かったのですが、小規模宅地の特例を適用することで
相続税額0円の申告書を当初申告で税務署に提出していました
私は、専業主婦で夫から家計の管理をすべて任されていました
私名義の預金8000万円は、毎月の家計を節約して
貯めた預金なので私の財産だと思っていましたが
相続税は、課税されるのでしょうか?
解説
今回のような場合の預金残高8000万円は、「借名財産」に該当し
相続税の課税対象財産となります。
一般的に、配偶者に限らず家族名義の預金は相続税の申告に当たって
相続税の課税対象になるかどうかのチェックが必要です
課税対象か否かの判断のポイントは二つあります
①まずその資金を稼いだのは誰なのか、という点です
今回の場合、被相続人のお給料を配偶者が配偶者名義の
口座でやりくりしたということですから、この8000万円の
名義は配偶者であっても、被相続人の財産と考えることができます
②その口座を誰が支配・管理していたのかということです
今回の場合、配偶者が被相続人の口座から資金移動して
配偶者名義の口座で家計のやりくりをしていたということです
つまり、被相続人は配偶者に日常生活に必要なお金の管理を
任せていたということです。しかし、このお金は被相続人が
稼いだお金ですから、日常生活以上の多額の支払い等については
被相続人が判断して支払っていました。
例えば、家を買う・車を買うといった場合の頭金等の
支払いは被相続人の承諾を得てから、配偶者名義の
口座から出金していました。と、いうことは配偶者名義の
預金残高について、被相続人が支配していたということになります
①②のチェックポイントから、配偶者名義の8000万円は
相続税の課税対象財産となります。
一般的な認識と若干ズレるかもしれませんが
このポイント①②は相続税の申告に当たっては
非常に重要なポイントです
相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです
1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります
2.土日はもちろん365日対応します
3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です
4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます
6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します
7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
8.初回のご相談60分無料・着手金無料
9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています
10.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています
遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記
雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事
塗装工事・増改築など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる
業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計1000件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
相続税の立替払いをしてもらって失敗しました
事例
数年前に父が亡くなりました
その際の財産総額は概算で3億円でした
遺産分割は、母が預貯金と自宅で合計1億円。
私は上場企業株を1億円、姉は駐車場1億円を相続しました
相続税の申告については、母親と税理士さんにすべて
お任せしていました。私と姉が本来すべき納税すべき
相続税も母親が立替払いをしてくれたようです
あれから数年が経って、今年の春に母親が亡くなりました
母親の財産は、父親から相続した財産の他に
固有の財産が1億円程度の預貯金と上場企業株が
あります。相続税の申告は、前回と同じ税理士に依頼しました
失敗したこと
母親の財産の資料を税理士さんに渡して
しばらくすると、上記の税金の立替払いについて
質問されました。
相続税の立替払いについては、贈与契約書や賃貸借契約書を
作成していませんし、母親に返済もしていません
そのため、母親の相続財産に立替払いの税額相当額が
債権として計上されると指摘されました。
結局、母親の相続財産総額が増えることになるので
相続税が当初の試算よりも増えることになってしまいました
母親が税金の立替払いしてくれた時は
何も考えていませんでしたが
結局、最終的に税金が増額してしまいました
相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです
1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります
2.土日はもちろん365日対応します
3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です
4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます
6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します
7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
8.初回のご相談60分無料・着手金無料
9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています
10.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています
遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記
雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事
塗装工事・増改築など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる
業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計1000件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
相続税を延納しようと思っていましたが・・・
事例
所有する財産に占める不動産の比率が高い場合に
延納申請をすることを前提にしていて
納税資金の調達を事前に準備していない事例が多いようです
例えば、駅前に大きなテナントビルや駐車場を所有するAさんは
不動産評価額が高騰したため、所有財産に占める不動産比率が
8割以上となっていました。また、2人の子は仲が悪いにも
関わらず遺言書の作成もしていません
そんな状態でAさんが急死しました
相続人である二人の子は、延納申請する予定でいましたが
長男と次男は、それぞれ苦しむことになりました
要件
延納申請するための要件は以下の通りです
(国税庁HPよりhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4211.htm)
(1) 相続税額が10万円を超えること。
(2) 金銭で納付することを困難とする事由があり、かつ、その納付を困難とする金額の範囲内であること。
(3) 延納税額および利子税の額に相当する担保を提供すること。
ただし、延納税額が100万円以下で、かつ
延納期間が3年以下である場合には担保を提供する必要はありません。
(4) 延納申請に係る相続税の納期限または納付すべき日(延納申請期限)までに
延納申請書に担保提供関係書類を添付して税務署長に提出すること。
したがって、期限内申告の場合は申告期限、更正又は決定の場合は
当該通知が発せられた日の翌日から起算して1か月を経過する日
期限後申告又は修正申告の場合は申告書の提出の日が延納申請期限となります。
失敗した原因
今回、2人の兄弟は上記要件の(3)で失敗しました
遺産分割協議がなかなか成立しない場合
相続財産は、すべて共有名義となります
その状態で、相続財産を延納申請の為の
担保に提供しようとすると、相続人全員が
同意することが必要となります
しかし、今回は次男が自己資金で未分割の
相続税額を期限内に納税することができたので
延納申請の為の担保提供に協力しませんでした
アドバイス
不動産比率が高い場合に、
延納や物納を前提に考えてる事例が
意外と多くありますが
現実的には、延納や物納は簡単ではありません
不動産比率が高い場合は、必ず
納税資金の事前準備に取組む必要があります
相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです
1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります
2.土日はもちろん365日対応します
3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です
4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます
6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します
7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
8.初回のご相談60分無料・着手金無料
9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています
10.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています
遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記
雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事
塗装工事・増改築など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる
業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計100件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
住宅取得資金贈与を利用したために、相続税の申告で失敗しました
事例
母が亡き後、父は実家で一人暮らしをしていました
実家は、100坪の面積で芦屋の閑静な住宅街にありました
父親は、会社を経営していましたが75歳で兄(長男)に事業承継して
引退しました。私(長女)は、会社の株式を相続しないかわりに
実家を相続することが家族間の話し合いで決まっていました
父親が亡くなる数年前に、住宅取得資金贈与の制度を利用して
父親から資金贈与を受けつつ、不足額は夫がローンを組んで
自宅を購入しました。・・・
問題点
父の住む実家は、路線価評価が非常に高く
私が相続することになっていました
小規模宅地の特例という制度があるのですが
税理士から、適用できないと言われました
小規模宅地の特例を適用できる相続人の条件は
1.配偶者
2.同居親族
3.家なき子
と決まっているそうです
私は、住宅ローン控除を利用して夫と共有名義の住宅を
購入したために、上記1.2.3のどれにも該当することなく
小規模宅地の特例を適用できないままで
実家を相続することになりました
解決策
自宅を購入する前に、
相続税に詳しい税理士さんに相談すべきだったと
反省しています
相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです
1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります
2.土日はもちろん365日対応します
3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です
4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます
6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します
7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
8.初回のご相談60分無料・着手金無料
9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています
10.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています
遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記
雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事
塗装工事・増改築など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる
業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計100件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
親族間でも借地権が発生します。
事例
Aさんが所有する遊休地に、長男Bさんが自宅を建築予定です
Bさんは、Aさんに地代を支払うつもりなのですが
Aさんは、地代をもらうと確定申告が必要になって
煩わしいので地代はいらないと考えてます
相続税の節税対策としては、Bさんは地代を支払うほうが
いいのでしょうか?
回答と解説
Bさんが、地代を支払うことにより
Bさんに税務上の借地権が発生します
その結果、Aさん所有の遊休地の税務上の評価額が下がるので
相続税対策としては有利になる場合があります
ただし、相続税対策として有利な結果となるために
考慮すべきポイントが2つあります
1.地代の金額をいくらで設定するのか、という論点です
地代は、高すぎても安すぎても税務上の借地権は0円となってしまいます
今回の場合、民法上の借地権は発生しますが税務上の借地権は
地代の金額次第ということです
2.借地権が最大に発生する地代を設定して毎月借地権を
支払う場合、地主さんの所有する土地の評価額は下がることになりますが
その一方で、金融財産は増えることになります
長期的に賃貸借契約が継続すると、土地の評価額の減額と
金融財産の増額が相殺されることになります
1,2から親族間で土地を賃貸借する場合には
地代を支払うかどうか、支払う場合は金額をいくらに設定するのか
について、慎重に検討する必要があります
相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
当事務所の強み
1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります
2.土日はもちろん365日対応します
3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です
4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます
6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します
7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
8.初回のご相談60分無料・着手金無料
9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています
10.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています
遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記
雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事
塗装工事・増改築など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる
業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
合名会社名義で収益物件を建てた場合の債務は、相続税の債務控除に計上できますか?
事例
父親の相続税対策として、父親名義の土地に収益物件を建てることを検討していますが
家賃収入によって、父親の金融財産が増えることを懸念していると
ハウスメーカーの顧問税理士から、合同会社を設立して
合同会社名義で収益物件を建てることを勧められました
その税理士の説明では、合同会社の債務はその残高を相続税の債務控除に
計上できるから、相続税の節税に大きな効果があるそうです
また、法人名義とすることによって家賃収入を家族に分散することもできるので
父親の金融財産が増えることも無いそうです
でも、そんな美味しい話があるんでしょうか?
回答と解説
その税理士の説明は、一部は正しいですが
一部は間違っています
まず、合名会社を設立しお父様を社員として
合名会社名義で融資を受けて収益物件を建てた場合に
お父様がお亡くなりになった時点での残債を
相続税の債務控除に計上できるというアドバイスは間違っています
会社法では、以下のように定めています
『580条:社員は、次に掲げる場合には連帯して持分会社の債務を弁済する責任を負う
1.当該持分会社の財産をもってその債務を完済することができない場合
607条:社員は・・・次に掲げる事由によって退社する
3.死亡
612条:退社した社員は、その登記をする前に生じた持分会社の債務について
従前の責任の範囲内でこれを弁済する責任を負う』
つまり、お父様がお亡くなりになったタイミングで合名会社が
借入金を返済できない場合は、残債を債務控除に計上できますが
そのような事態にはなる可能性は極めて低いからです
収益物件を建てるにあたっては、銀行の厳重な審査があるはずです
それにもかかわらず、会社の財産をもって残債を完済することが
できなくることは通常はあり得ないからです
うかつに、この税理士の助言を信じて相続税対策と所得税対策の
一石二鳥を狙っても、相続税対策には効果が無いということに
ご注意ください

相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
当事務所の強み
1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります
2.土日はもちろん365日対応します
3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です
4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます
6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します
7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
8.初回のご相談60分無料・着手金無料
9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています
10.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています
遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記
雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事
塗装工事・増改築など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる
業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください
代襲相続人の孫を養子縁組した場合の相続人の人数は? 【 税法と民法 】
質問
私は三男で、母は数年前に亡くなりましたが
父は健在です。私には二人の兄がいたのですが
先日、長男が不慮の事故で亡くなりました。
長男には、今年成人したばかりの長女がいます
父は、相続税対策の為に長男の長女を養子にすることを
考えているようです
このような場合、相続人の数はどのように数えるのでしょうか?
また、それは民法と相続税法で同じですか?
なお、次男は自分自身の事業が大成功したので
父親からの相続は適法な手続きで放棄しています。
回答と解説
民法上の相続人は2人となります
本来は、長男の長女・次男・三男の3名が相続人となりますが
次男は適法に相続放棄しているので、長男の長女・三男の2人だけが
民法上の相続人となります
一方で、民法上の相続分は長男の長女が2/3・三男は1/3となります
相続人は2人ですが、長男の長女は長男の代襲相続分と養子としての相続分が
あるからです。
次に、相続税法上の法定相続人の数は、長男の長女・次男・三男の3人
となります。次男は適法に相続放棄の手続きを済ませていますが
相続税の計算上は、法定相続人の人数にカウントして基礎控除の額を
計算します
最後に、相続税の総額の計算上適用される法定相続分については
長男の長女が1/2・次男が1/4・三男が1/4となります
このように、養子縁組すると民法上も相続税法上も二重資格の相続人の
問題が発生しますのでご注意ください
相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
当事務所の強み
1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります
2.土日はもちろん365日対応します
3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です
4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます
6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します
7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
8.初回のご相談60分無料・着手金無料
9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています
10.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています
遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記
雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事
塗装工事・増改築など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる
業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
相続開始から4カ月経過していますが、準確定申告はどうすればいいですか?
事例
今年の5月に父親が亡くなり
相続税の申告が必要なのですが
その前に、所得税の準確定申告が必要です
申告期限が迫っているのですが、まだ必要な
資料を集めていません。どうすればいいでしょうか?
父親の所得は、公的年金と上場企業株式の配当金がわずかに
あるだけです。直近数年の父親の確定申告書を
確認すると、毎年還付申告だったようです
回答
準確定申告の申告期限は、相続開始の日から4カ月です
しかし、還付の場合4カ月経過後の申告であっても
問題ありません。
解説
今回のような準確定申告の場合揃えるべき必要な資料は
・公的年金の準確定申告書
・介護保険の支払金額の証明書
・後期高齢保険の支払金額の証明書
・配当金の支払通知書
です
なお、相続人が複数人で準確定申告の還付税金を
相続人間で分割せずに、ひとりの相続人が
受取る場合は、準確定申告書に付表を添付するだけでなく
委任状も添付する必要があります

相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
当事務所の強み
1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります
2.土日はもちろん365日対応します
3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です
4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます
6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します
7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
8.初回のご相談60分無料・着手金無料
9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています
10.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています
遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記
雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事
塗装工事・増改築など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる
業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
http://www.不動産賃貸税理士.com/
******************
亡くなる直前に口座から出金した現金の扱い
事例
父は亡くなる直前に認知の症状が進んでしまったために
長女と母親が、父親の口座からキャッシュカードを利用して
資金を出金し、長女と母親の口座に移しました
その金額は総額で8000万です
その結果、相続開始時に父親の財産は
自宅不動産と預貯金1億2000万円でした
相続税の申告に当たって、税理士に相談したところ
直前に出金した8000万円も相続税の課税対象財産に
計上すべきという助言を頂きました
この8000万円は申告すべきでしょうか?
回答と解説
直前出金の8000万円は、税理士の助言通り
相続税の課税対象財産として計上する必要があります
相続税の申告に当たって
相続開始の日の残高だけが課税対象財産ではありません
今回のように、長女と母親が直前に出金した8000万円は
父親が長女や母親に贈与した資金移動ではありません
たとえ、今回と違って贈与が成立していた場合といえでも
生前贈与加算の対象となります
長女と母親の資金移動は、申告しなければ
税務調査によって必ず指摘されます
税務署は、被相続人(父親)の銀行口座を過去10年に
遡って資金移動を調べます
また、相続人の口座も同じく調査することができます
その過程で、今回のような資金移動は必ず
発見されます。
ですから、相続税の申告書には
現金として8000万円を計上する必要があります
相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
当事務所の強み
1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります
2.土日はもちろん365日対応します
3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です
4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます
6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します
7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
8.初回のご相談60分無料・着手金無料
9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています
10.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています
遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記
雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事
塗装工事・増改築など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる
業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
借入金の連帯債務は相続税の申告で控除できますか?
事例
Aさんは、相続した土地で賃貸住宅経営をすることを
考えています。土地はAさんの単独の名義ですが
銀行から提示された条件は、長男Xとの連帯債務とすることでした
賃貸住宅は、Aさんの単独名義で建てることになりますから
家賃収入は、Aさんの口座に入金されます。
このような場合に、Aさんの相続に当たって
銀行借入の残高は債務控除できますか?
回答
連帯債務者であるAさんとXさんとの間で
債務者間で負担割合の取り決めがあるかどうかによります
解説
Aさんが将来亡くなった場合の
相続税の申告書の作成に当たって
連帯債務者間で債務の負担割合を決めている場合
Aさんの負担割合部分は、Aさんの債務として
債務控除の対象となります
一方で、負担割合の取決めが無い場合は
債務金額の50%相当が債務控除の対象となります
根拠条文は、民法427条です
相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
当事務所の強み
1.すべての案件のお客様との面談は所長自らが担当します
2.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
3.相続税の申告実績は20年間で800件以上です
4.相続税の節税相談は20年間で2000件以上です
5.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
6.土日はもちろん祝日、お盆、年末年始も対応します
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
死因贈与と遺贈・・・どっちがいいの?
事例
Aさんは妻と子が2人います
先のことを考えて、顧問弁護士と遺言書の作成を始めましたが
Aさん所有の甲土地については、孫X君の名義にしてあげようと
考えてます。その方法として、遺贈という方法と死因贈与と
言う方法があると、弁護士から説明されました。
どちらがいいのでしょうか?
回答
どちらも、それぞれのメリットがありますので
個別具体的な事情に応じて選択する必要があります
解説
遺贈も死因贈与も、ほぼ同じ効果がありますが
微妙に異なります
遺贈は、遺言書に記載することによりAさん名義の甲土地をX君名義
とすることができます。
死因贈与の場合、Aさんが生前にX君と甲土地の贈与契約書を締結
しておく必要があります。この贈与契約書の作成した日付については
Aさんの相続税の申告時に税務署が確認しますので、公正証書で
契約書を作成されることをお勧めします
なお死因贈与の場合は、契約書作成後にAさんからX君への所有権移転の
仮登記をすることもできます。
いずれの方法も、Aさんの死後に甲土地の名義をX君に変更するためには
有効な手段です。
しかし、いずれの方法も遺留分の計算対象となりますので
事前に財産増額及び遺留分の金額を計算しておくことを
お勧めします
税金面では、いずれも相続税の課税対象となりますが
X君は法定相続人ではありませんので、どちらの場合でも
登録免許税と不動産取得税は、課税されることになります
財産を受取るX君の立場からすると、遺贈の場合は
遺言書が開示された後で、甲土地の相続を放棄することができます
しかし、死因贈与の場合は事前に双方の合意があるわけですから
X君が相続を放棄することはありません。
法定相続人以外の人物に財産を相続させる方法として
遺贈と死因贈与がありますが、それぞれにメリット・デメリットが
ありますので、状況に応じて使い分ける必要があります
相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
当事務所の強み
1.すべての案件のお客様との面談は所長自らが担当します
2.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
3.相続税の申告実績は20年間で800件以上です
4.相続税の節税相談は20年間で2000件以上です
5.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
6.土日はもちろん祝日、お盆、年末年始も対応します
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
兵庫M&A・事業承継支援センターのHP
******************
個人の土地を同族会社に貸す場合の留意事項
事例
社長のAさんは、Aさんが株主(80%所有)で社長である株式会社X(同族会社)に
Aさんが100%地主の土地甲を貸すことにしました。
土地の利用目的は、本社ビルの建設です
本社ビル完成後は、X社はA社長に毎年1800万円の地代を
支払う契約書を締結しました。また、権利金等の授受は
ありません
年間1800万円は通常の地代に相当し、契約書に
将来X社がこの土地を無償でA社長に無償で返還する」旨の
記載はありません
上記のような状況で、課税上問題はありませんか?
回答
・A社長・・・みなし譲渡課税は無し
・X社・・・借地権相当額の利益について法人税課税
・A社の他の株主・・・贈与税課税
解説
・AさんがX社に対して無償で借地権の設定をしていますが
このことは、資産の移転ではないのでA社長にみなし譲渡課税が適用される
リスクはありません
・借地権の設定にあたって、権利金の授受が行われる慣行のある
地域で借地権を無償で設定した場合、その法人は借地権の評価額に相当する
雑収入(利益)に対して法人税が課税されることになります
・AさんがX社に無償で借地権を設定させてしまったことにより
X社の株価は上昇することになります。その場合、X社のAさん以外の
株主に対して『贈与』したことになります。そのため、他の株主に対して
贈与税が課税されます
相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
当事務所の強み
1.すべての案件のお客様との面談は所長自らが担当します
2.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
3.相続税の申告実績は20年間で800件以上です
4.相続税の節税相談は20年間で2000件以上です
5.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
6.土日はもちろん祝日、お盆、年末年始も対応します
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
役員の死亡退職金の受取と相続税の申告
事例
被相続人Aさんは、X社の代表取締役でした
Aさんの法定相続人は、配偶者のBさん・長女のCさん・長男のDさんです
Aさんの財産は、合計5億円でした
Aさんの遺産分割協議はまだ成立していませんが
相続税の申告期限の1週間前の先日X社の取締役会で
Aさんの死亡退職金1億2000万円がBさんに
支給されることが決定されました。
これはX社の役員退職金規程に基づくものではありません。
このような状況で、相続税の申告に当たって
死亡退職金の扱いについて教えてください
回答
1.死亡退職金は、相続財産ではなく受給権者であるBさんの
固有の財産となるので、分割の対象とはなりません
2.死亡退職金は、役員退職金規程が無い会社であっても
Bさんの固有の財産となります
解説
1.死亡退職金については、最高裁の判例(昭和55年11月27日)で
「本件退職金規程は、もっぱら職員の収入に依拠していた
遺族の生活保障を目的とし、民法とは別の立場で受給権者を
定めたもので、受給権者たる遺族は、相続人としてではなく
右規程の定めにより直接これを自己固有の権利として取得する」
と判示しました。
2.退職金規程が無い場合でも、最高裁の判例(昭和55年11月27日)で
権限のある法人の機関が決定した退職金・受給権者は
相続財産・相続人とは別のものとして認定しました。
X社の取締役会でBさんが受取る役員退職金の支給日が申告期限
までに決定したので、その死亡退職金はBさん固有の財産となり
相続税の課税対象財産になります
参考までに、相続税法基本通達3-25には以下のような記載があります
1.退職金規程がある場合は、規程に基づき受取ることになる者
2.退職金規程が無い場合あるいは退職金規程の適用を受けない者の場合は
退職金を現実に取得した者又は、相続人全員で協議して受取人を
決めた場合は、その決められた者
上記以外の場合は、相続人全員が受取人となり各人の受取金額は
各人均等となります。
これは、退職金が相続財産ではないことから、その受取る権利は
法定相続割合とは関係なく、均等の割合になります
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
不動産の売買契約中に父が死亡しました。相続税の申告と所得税の申告はどうしたらいいですか?
事例
Aさんは、5月末に収益物件Zの土地・建物を仲介業者を通してXさんに1億円で売却する旨の
契約書を締結しました。契約締結時に手付金として2000万円を受取りましたが、残りの
8000万円は、7月末に全額を受取る予定でした。また、物件引渡しと名義変更も同時に
行う予定でした。
しかし、6月末にAさんは死亡し相続人であるBとCがすべての財産を50%づつ
相続することになりました。このような場合にBとCは収益物件Zに関する相続税の申告と
譲渡所得の申告をどのようにすればいいでしょうか?
回答
相続税の申告書には、残余財産請求権(8000万円)を計上します
譲渡所得の申告は、Aさんの準確定申告あるいはBとCそれぞれの確定申告
のいずれかを選択できます
解説
相続税の申告について、残余財産請求権と収益物件Zのどちらを
課税対象財産に計上すべきか悩ましいところです
しかし、この論点については最高裁の判例で『残余財産請求権』という
結論が出ています。
譲渡所得の申告については
Aさんの準確定申告あるいはBとCそれぞれの確定申告のどちらでも
申告可能です。しかし、以下の点で注意が必要です
・債務控除
➡準確定申告の場合は〇
確定申告の場合は✖
・住民税
➡準確定申告の場合は課税なし
確定申告の場合は課税あり
・取得費加算
➡準確定申告の場合は適用無
確定申告の場合は適用あり
以上の3点に留意して
いずれを選択するのかを決める必要があります
相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
当事務所の強み
1.すべての案件のお客様との面談は所長自らが担当します
2.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
3.相続税の申告実績は20年間で800件以上です
4.相続税の節税相談は20年間で2000件以上です
5.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
6.土日はもちろん祝日、お盆、年末年始も対応します
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
居住用不動産の贈与をあった年に配偶者が死亡した場合の税金は?
事例
Aさんは婚姻関係が40年以上になるので夫であるBさんから
自宅の土地及び家屋(評価額1800万円)の贈与を受けました
しかし、Bさんはその直後に急死してしまったのです
さて、このよう場合相続税の申告と贈与税の申告は
どうなるのでしょうか?
回答
相続税は、課税対象外
贈与税は、申告して無税
となります
解説
資産の贈与があっても、相続開始の7年前の贈与財産については
相続税の課税価格に算入されてしまいます
しかし、その贈与財産が配偶者控除の適用を受けた居住用財産
である場合は、その特定贈与財産の評価額までは受贈配偶者の
相続税の課税価格に加算しないこととされています
(相続税法19条)
その一方で、生前贈与の加算対象とならない上記特定贈与財産については
その贈与が贈与した配偶者の相続開始の年に行われたものであったとしても
非課税財産に該当しないため、贈与税の申告が必要となります
この事例では、住宅の評価額が2000万円未満ですから
贈与税の申告をしても贈与税額は0円となります
神戸・芦屋・西宮エリアで相続税対策及び
相続税申告業務は、是非お任せください
当事務所の強み
1.すべての案件のお客様との面談は所長自らが担当します
2.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
3.相続税の申告実績は20年間で800件以上です
4.相続税の節税相談は20年間で2000件以上です
5.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
6.土日はもちろん祝日、お盆、年末年始も対応します
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
子名義の家屋で一人暮らししていた父が死亡した場合の小規模宅地の特例
事例
私は、父親名義の土地甲に私名義で家を建てて
私たち家族と父と同居していました。
しかし、家庭内のトラブルが原因で私たち家族は
近くの賃貸マンションに引っ越しし、父親は
父名義の土地に私が建てた家に独りで暮らすようになりました
その後、5年が経って父が亡くなりました
父親名義の土地は、私が相続し私名義の家で再び
私たち家族の生活が始まることになります
この場合、小規模宅地の特例は適用できますか?
ただし、私は父親に地代を支払っていませんし
父親も私に家賃を支払っていません
回答
小規模宅地の特例は適用できます
解説
「被相続人等の居住の用にきょうされていた宅地等」の範囲を定めた
措置法通達69の4-7(1)の後半部分には以下の記述があります
「被相続人が所有していたもの又は被相続人の親族が所有していたもの
の敷地の用に供されていた宅地等」
ただし、カッコ書きで以下の記述があります
(当該家屋を所有していた被相続人の親族が当該家屋の敷地を
被相続人から無償で借り受けており、かつ、被相続人が当該
家屋を当該親族から借り受けていた場合には、無償で借り受けて
いたときにおける当該家屋に限る。)
今回のように、双方ともに無償の場合には
小規模宅地の特例が適用されます
親族間で土地や建物の貸し借りを行う場合には
相続税対策も視野に入れる必要がありそうです
神戸・芦屋・西宮エリアで相続税対策及び
相続税申告業務は、是非お任せください
当事務所の強み
1.すべての案件のお客様との面談は所長自らが担当します
2.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
3.相続税の申告実績は20年間で800件以上です
4.相続税の節税相談は20年間で2000件以上です
5.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
6.土日はもちろん祝日、お盆、年末年始も対応します
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
遺産分割協議が成立する前に土地を売却した場合に、所得税の申告は???
事例
Xさんが亡くなり、相続人はA・B・Cの3人です
Xの相続財産に占める不動産の比率は80%を
越えている為、X名義の預貯金だけでは納税資金が
不足しています。また、相続人のB・Cは不動産よりも
預貯金を相続したいと考えています。
そこで、AはX名義の不動産を全部売却してその売却代金を
法定割合で1/3づつ確定申告すればいいと考えています
しかし、BとCは売却代金を法定割合で分割することに
同意するかどうかわかりません
質問
上記のような場合、不動産譲渡所得の確定申告は売却代金の
1/3づつで申告すればいいですか?
回答
お尋ねの件について、一般的には不動産の相続登記割合
つまり1/3づつ売却代金を分配して、確定申告も
同じ比率で提出することになります
しかし、相続人が「土地の売却代金を一括して共同相続人の
1人に保管させて遺産分割の対象に含めることに
合意する」場合は、最終的な遺産分割協議書に記載の比率で
売却代金を分割して、相続税及び所得税の申告を行うことになります
【参考】最高裁昭和54年2月22日第一小法廷・・・
相続税の申告とご相談は、神戸・芦屋・西宮で
相続専門税理士として24年営業を続けている
私の事務所にお任せください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
古い木造アパートを相続したんですが・・・交換ってできるんですか?
事例
私は、親から古い木造アパートを相続しました。
相続から5年経過しましたが、建物劣化が激しく建て替えるか
売却するか検討していました。
しかし、不動産業者の担当者から「隣の街の月極駐車場と交換して
その土地で新しく賃貸住宅を建設することができる」と
言われました。そんな都合のいい話は本当に実現するのでしょうか?
回答
要件を満たせば、税務上の問題をクリアできます
解説
いわゆる交換の特例を適用するための要件は以下の通りです
1.交換譲渡資産と交換取得資産はいずれもこ定子さんであること
2.交換譲渡資産を1年以上所有していたこと
3.交換取得資産は相手方が1年以上所有していたこと
4.交換譲渡資産と交換取得資産は同一種類の資産であること
5.交換後は、交換取得資産を交換譲渡資産の交換直前の用途と
同一の用途に供すること
6.交換譲渡資産と交換取得資産の時価の差額が、これらの時価のうち
高い金額の20%以下であること
これらの要件のうち、今回論点となるのは5番の要件です
交換譲渡資産は木造賃貸アパートの敷地で
交換取得資産は月極駐車場の土地です
単純に、これだけでは同一用途とならないため
交換の要件は満たしません
しかし、今回の交換取得資産である駐車場の立地が住宅地であり
既存の構築物を取壊したり造成工事をすることなく
いつでも建物を建設が可能な土地であれば宅地と同様に
取り扱うことができると考えられます
相続税の申告業務は、神戸・芦屋・西宮で
相続専門税理士として24年営業を続けている
私の事務所にお任せください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
換価分割の留意点 3月10日の続き
このHPで換価分割の概要については3月10日に
解説しましたが、今日は前回書ききれなかった留意点を
記載します
事例
例えば、先祖代々の土地に父親Aさんが住んでいました
Aさんの配偶者は以前に亡くなっていましたが、Aさんの長女Xさんは
同居していました。またAさんにはXさん以外に長男Yさんと次男Zさんの
相続人がいます。
Aさんの遺産は、AさんとXさんが住んでいた自宅の不動産100坪(評価9000万)
と預貯金1億2000万です。遺産分割に当たっては兄弟で喧嘩はしていませんが
いろんなパターンを考えているようです
兄弟全員が、自宅をいずれ売却することについて賛成しています
そこで、分割パターン別に留意点を検討することになりました
検討
留意点1:XさんはAさんと同居していたので小規模宅地の特例が適用できます
小規模宅地の特例のメリットを最大限活かすためにはXさんが単独で
自宅不動産を相続する必要があります。しかしその場合、相続割合が
法定割合と大きく乖離するという問題があります
留意点2:留意点1の論点を解消するために、自宅不動産を換価分割する場合
法定分割となります。しかし、小規模宅地の特例のメリットを1/3しか
活かすことができません。今回の相続税ではXさんの単独相続と法定割合の相続では
3兄弟の相続税総額に700万円の差額が発生します。これは大きな問題です
留意点3:留意点2の分割パターンは、小規模宅地の特例のメリットが1/3となり
なおかつ相続税も700万円増加しますが、3兄弟平等というメリットがあります
これが換価分割の最大のメリットです
しかし、この方法も一つ問題があります。換価分割の為に自宅を売却した際の
所得税の金額について、XさんとYZさんとでは大きな差額が発生します
つまり、Xさんは実家でAさんと同居していたので譲渡所得税の計算にあたって
●居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例と
●長期譲渡所得に軽減税率の特例を適用できるのです
せっかく仲のいい兄弟が遺産分割を平等にしても、譲渡所得税で大きく
差額が発生します。
このように、換価分割を実施する際には様々な論点が発生します
税理士は、分割案のパターン別に税額計算を行うことはできます
相続税の申告業務は、神戸・芦屋・西宮で
相続専門税理士として24年営業を続けている
私の事務所にお任せください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
相続開始の3年以内に取得して賃貸住宅経営を始めた宅地の評価額
事例
父は、祖父の代から引き継いだ土地Aに
16年前に賃貸マンションを建設して賃貸住宅経営に
取組んでいました。借入金の残高もかなり減少したため
2年前に土地Bを取得して新たに賃貸マンションを建設して
2つ目の賃貸住宅経営を始めました
しかし、父親は先月突然亡くなりました
遺言には、土地Aとその上に建つマンションは長男X
土地Bとその上に建つマンションは次男Yが相続すると記載が
ありました。
質問
土地A及びBは、いずれも賃貸住宅の建つ土地です
どちらの土地も、小規模宅地の特例を適用することが
できるでしょうか?
回答と解説
要件を満たせば、ABともに小規模宅地の特例の適用対象
となります
相続税の改正によって、相続開始の直前3年以内に
新たに賃貸住宅経営の対象となった宅地は
小規模宅地の特例の適用対象に該当しないことと
なりました
しかし、上記改正も
被相続人が、相続開始の日まで3年を超えて引き続き賃貸住宅経営を
継続しているには、小規模宅地の特例の適用対象に該当します
この特例の改正は、間違いやすいので
充分に注意が必要です
相続税の試算・申告のご依頼は
相続税を専門とする税理士事務所に依頼することを
お勧めします
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計600件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
生命保険金だけではなくて、生命保険契約にも相続税が課税!!!
相続税の申告に当たって
受取った生命保険金だけではなくて
生命保険契約にも相続税が課税されることを
ご存知ない方が多いので
解説します
事例
父親は、以下のような2つの生命保険契約を締結していました
1.契約者:父親 被保険者:父親 受取人:長男
2.契約者:父親 被保険者:孫 受取人:満期の場合は孫、孫死亡の場合は長男
このような生命保険契約を締結している父親の相続が開始しました
なお、2の生命保険については満期を迎えていません
このような状況で、相続税の課税関係はどうなるでしょうか?
解説
1の生命保険について、相続税の課税対象になることは問題ありません
しかし、2の生命保険について相続税の課税対象となることに
気づいていない場合が多くあります
2の生命保険は、父親が保険料を支払っていて
被保険者が孫であるため、父親が亡くなっても
保険金は支払われることはありません
ですから、生命保険の権利が相続税の課税対象となります。
また、この2の生命保険契約は1と違ってみなし相続財産ではありません
そのため、遺言書に記載がない限り孫がこの契約の権利を
相続できません。
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
遺産分割に当たって死亡保険金の受取人が保険金の一部を他の相続人に・・・
遺産分割に当たって死亡保険金の受取人が保険金の一部を他の相続人に支払った場合の税金
被相続人Xの相続人は長男A、次男B、三男Cの3名のみ
相続財産は、自宅(5000万)と賃貸マンション(3000万)のみ
生命保険契約は、6000万円でAが受取人となっている
遺産分割案の概要
第1案:Bは自宅、Cは賃貸マンションを相続し
Aは生命保険を受取りつつ、Aは生命保険6000万円から
2000万円をCに支払う
第2案:Bは自宅、Aは賃貸マンションと生命保険6000万円
Cは、Aから2000万円を支払ってもらう
第1案と第2案の税金
結論は、
第1案では、A,B,Cそれぞれに相続税が課税されるとともに
Cに贈与税が課税されます
Aは、生命保険を受取るのみで遺産を相続しません
そのため、生命保険金から2000万円をCに支払うことは
遺産分割に関係なく、単なる贈与となります
第2案では、代償分割における代償債務の履行となるため、Cに贈与税は課税されません
A,B,Cそれぞれに相続税が課税されます
『代償分割に係る代償金として、代償債務者である相続人から
その者が取得した積極財産の価額を超える代償金を受領した場合には、
その積極財産の価額を超える部分は、現物をもってする分割にかえる
代償債務に該当せず、代償債務者から他の相続人に新たに経済的利益
を無償にて移転する趣旨でされたものと言うべき』・・・過去の裁判事例から抜粋
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計600件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
夫婦間で居住用財産を贈与したのですが・・・思わぬ落とし穴が・・・
夫婦間で居住用財産を贈与しました
私たち夫婦は、今年で結婚生活が30年となります
私の年齢も60歳になります。
妻への日ごろの感謝の気持ちをこめて
何かできないか、と考えていたところ
居住用財産の夫婦間贈与の制度をネットで見つけました
そこで早速我が家の評価額を調べると
土地が5000万円・建物が800万円ほどであるが分かりました。
建物はこれからも評価額が下がるようなので
土地の2110万円相当を贈与で妻の名義にすることに
しました。
ところが、思わぬ落とし穴が
早速、司法書士の先生に依頼して
契約書を作成していただいて法務局で登記していただくことに
なりました
しかし、ここで登録免許税が42万円も課税されることを
初めて知りました。私から妻に自宅の土地の名義を
変更するだけで42万円も税金を支払うのは想定外でしたが
当初の目的を達成するために、名義変更の登記を依頼しました
そして、さらに数カ月後に県税事務所から不動産取得税の
納付書が届きました。その金額が32万円でした
私から妻へと贈与税の非課税枠の範囲内で自宅の土地の
名義変更をしたのですが、結局74万円も納税することに
なってしまいました
更に、ショックなことが
その後、贈与税の申告の為に税理士さんと
お話しをしていると
更にショックなことを聞かせれました
・登録免許税の税率は、相続の場合は贈与の場合の1/5となること
・不動産取得税については、相続の場合は非課税であること
・夫婦で住んでいる自宅について、相続税の申告に当たっては小規模宅地の特例が
適用できること
これらの知識を事前に知っていれば、わざわざ74万円も納税して
自宅の土地の名義を妻に変更しなかったと思います
税金については、事前にプロに相談すべきだったと
いまさらながら反省しています
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
死亡保険金で代償分割した場合の税金って???
質問
Aさんの相続財産を長男Xと次男Yで分割協議しました
Aさんの財産構成は、
そのほとんどがAさんの経営していた工場の土地と建物
(評価額1億円)でした。
現預金は2000万円程度でした
その一方で、AさんはAさんが契約者・被保険者となり
受取人を長男Xとする生命保険契約1億円を締結してました
長男Xと次男Yが遺産分割協議をした結果
現預金2000万円はXが相続して
工場の土地と建物はYが相続することになりました
しかし、このままではYは納税資金が不足するため
代償分割でXからYに代償金を支払うことになりました
このような遺産分割の場合、XとYの課税関係はどうなりますか?
回答
Xの受取る生命保険金は、相続財産ではなくX固有の財産となります
代償分割は、相続財産の範囲内で代償金を支払うのであれば
相続税だけが課税されます
今回、Xの相続財産は現預金2000万円のみです
生命保険金1億円は相続財産ではなく、固有の財産です
ですから、XからYに支払う代償金が2000万円を超えると
Xの相続財産を超える金額をYに代償金として
支払うことになってしまいます
その結果
Xの相続財産>代償金 の場合は、Yは相続税のみの課税
Xの相続財産<代償金 の場合は、2000万円を超える金額について
Yは贈与税が課税されます
充分にご注意ください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
孫の教育費をおじいちゃんが負担した場合の贈与税って???
孫の教育費をおじいちゃんが負担した場合の贈与税って???
少子高齢化により、子供や孫の教育費を祖父母が負担するケースは
増加傾向にあるようです
そこで、教育費の贈与について課税関係や限度額についての
お問い合わせが多くあります
教育資金贈与
一般的には、教育資金贈与という制度が知られています
詳細については、下記URLから国税庁のHPを
ご覧ください
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm
この制度は、簡単に申し上げますと
金融機関に教育資金の為だけの特別な口座を
設けます。この口座から支払った教育費に関しては
非課税とする制度です。
相続税対策で、使いやすそうな制度ですが
実際に利用するとなると、様々な制限があって
この制度の利用を諦める方もいらっしゃるようです
実は、非課税ってご存知ですか???
実は、上記の教育資金贈与という制度を利用しなくても
教育費の贈与は、そもそも贈与税が課税されない
つまり、非課税ってご存知でしょうか?
教育資金の贈与は、非課税なんです
そもそも、民法では夫婦・直系血族等は相互に扶養する義務を
定めています
上記民法の定めに基づいて、贈与税では非課税財産を
以下のように定めています
「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした
贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」
この定めに基づき、おじいちゃんが孫の教育費を負担することに
対して贈与税は課税されないことが明らかです
それでは、「通常必要と認められるもの・・・」
の記載については、どこまでが非課税となるんでしょうか???
この点について、詳細を記載すると長くなるので
ここでは割愛させていただきますが
大原則として、教育資金の贈与は贈与税が課税されない
ということをご理解ください・・・ただし
通常必要と認められるものに限ります
相続税及び贈与税の対策と申告は
相続税専門の税理士にお任せください
神戸・芦屋・西宮のお客様をメインにしている
相続税専門税理士事務所は、こちらです
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
兵庫M&A・事業承継支援センターのHP
******************
遺産分割協議が成立しない場合の相続税の申告書
遺産分割協議が成立しない場合
【質問】
相続税の申告書は、相続開始の日から10ヶ月以内に税務署に提出
しますが、その際に遺産分割協議が成立していない場合もあります。
その場合の相続税の申告書は、どのような申告になりますか?
複数の税理士が申告する場合もあります
【回答】
(1)複数の税理士が・・・
遺産分割がもめてまったくまとまらない場合に
すべての相続人が個別に税理士と契約して相続税の
申告書を作成することもありえます。
相続税の申告書を作成するために必要な情報を
すべての相続人が同じ情報を入手できません
そのため、被相続人が同じであっても
相続税の申告書に記載の財産と債務が完全に一致しない場合が
あります
(2)納税資金を確保するために
遺産分割がもめてまったくまもらなくても
申告期限=納税期限であることに変わりありません
相続人全員が自己資産から納税資金を賄うことができる場合は
問題ありませんが、そうでない場合が問題となります
納税資金を確保するために、相続財産に含まれる
金融財産の一部だけでも先に遺産分割をまとめる必要があります
(3)相続税をすこしでも少なくするために
遺産分割協議が成立していなければ適用できない特例があります
たとえば、小規模宅地の特例は対象となる土地の
遺産分割協議が成立していなければ適用できません。
もちろん、いったん未分割で申告書を提出し
遺産分割協議が成立後に小規模宅地の特例を適用して
更正の請求を税務署に提出することもできます
相続税の申告書類作成業務は、相続税の申告期限までに
遺産分割協議が成立して、なおかつ納税資金を確保しておく必要があります
もちろん、遺産分割協議は相続人間あるいは弁護士を交えて
行うため税理士は関与できません。
しかし、税理士は
未分割の場合にはどのような申告書を提出することになるのか
あるいは、未分割か否かによって税負担にどれだけの差が発生するのか
という、お客様の税金に対する疑問に臨機応変に対応する必要があります
相続税の申告業務と相続税対策は
相続税専門の税理士に相談することを勧めます
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
換価分割って・・・?
相続財産が不動産だけ・・・どうやってわけるの?
相続財産のうち、不動産の占める比率が高く
相続人全員で納得できる分割ができない場合など
換価分割という方法があります
換価分割とは???
換価分割とは、例えば・・・
相続財産が評価額3000万円の土地だけで
法定相続人が3人の場合に、土地の所有権を1/3づつ
登記する方法もありますが
全員が、土地よりもお金が欲しい場合もあります
そんな場合、土地を換金して分ける方法が
換価分割です。つまり、土地を換金してそのお金を
分けるという方法です
具体的な方法
一般的に換価分割の場合、不動産売却手続きを簡単にするために
登記簿上の相続人の名義は、相続人のうち代表者1名だけとします
その後、相続財産の不動産を相続人代表が売却して
売却代金を、他の相続人に分配する方法が、換価分割の
具体的な流れになります
留意事項
換価分割は、不動産比率が高く
現金で相続を希望する場合に多く活用される
遺産分割方法ですが、税務上留意すべきポイントが
一つだけあります
それは、遺産分割協議書に
換価分割する旨を明記する必要があるということです
その記載がないと、資金の流れだけを見ると
親族間の贈与と誤解されるリスクがあります
相続税の申告業務は、神戸・芦屋・西宮で
相続専門税理士として24年営業を続けている
私の事務所にお任せください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
相続税の申告書に添付する印鑑証明書の入手日について
遺産分割協議書と印鑑証明書を税務署に提出する理由
遺言書が作成されている場合以外は
相続税の申告書には、遺産分割協議書と印鑑証明書を
添付する必要があります
相続税額の計算に当たって適用される特例には
いくつか種類がありますが
小規模宅地の特例などは、遺産分割の内容によって
摘要の可否が判定されます
そのため、相続税の申告書には必ず遺産分割協議書と
印鑑証明書を添付する必要があります
提出する書類の入手日付
お客様から、相続税の申告書に添付する印鑑証明書の入手日について
お問い合わせをいただくことがありますが、
税務署に提出する書類は、相続開始の日以降であれば
いつでもOKです。これは、印鑑証明書だけではなくて
戸籍・住民票などの書類も同様です
効率のいい遺産収集
印鑑証明書は、最終的に土地の名義変更や
預金の解約などで必要になります
ですから、相続開始直後に印鑑証明書を
入手する必要はありません。
むしろ遺産分割協議が成立する頃に
入手すれば、不動産の名義変更や預金の
解約手続きを済ませた後で
印鑑証明書を税務署に提出することができます
相続税の申告業務・遺産収集業務は
効率よく作業を進めないと相続人の皆さんに大きな
ストレスが負担になります
相続税の申告業務は、神戸・芦屋・西宮で
相続専門税理士として24年営業を続けている
私の事務所にお任せください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************