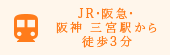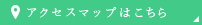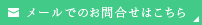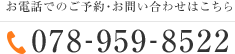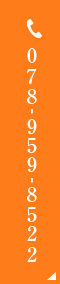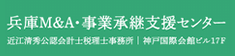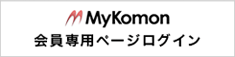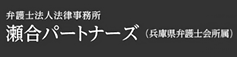住宅取得資金贈与を利用したために、相続税の申告で失敗しました
事例
母が亡き後、父は実家で一人暮らしをしていました
実家は、100坪の面積で芦屋の閑静な住宅街にありました
父親は、会社を経営していましたが75歳で兄(長男)に事業承継して
引退しました。私(長女)は、会社の株式を相続しないかわりに
実家を相続することが家族間の話し合いで決まっていました
父親が亡くなる数年前に、住宅取得資金贈与の制度を利用して
父親から資金贈与を受けつつ、不足額は夫がローンを組んで
自宅を購入しました。・・・
問題点
父の住む実家は、路線価評価が非常に高く
私が相続することになっていました
小規模宅地の特例という制度があるのですが
税理士から、適用できないと言われました
小規模宅地の特例を適用できる相続人の条件は
1.配偶者
2.同居親族
3.家なき子
と決まっているそうです
私は、住宅ローン控除を利用して夫と共有名義の住宅を
購入したために、上記1.2.3のどれにも該当することなく
小規模宅地の特例を適用できないままで
実家を相続することになりました
解決策
自宅を購入する前に、
相続税に詳しい税理士さんに相談すべきだったと
反省しています
相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです
1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります
2.土日はもちろん365日対応します
3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です
4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます
6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します
7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
8.初回のご相談60分無料・着手金無料
9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています
10.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています
遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記
雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事
塗装工事・増改築など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる
業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計100件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
亡くなる直前に口座から出金した現金の扱い
事例
父は亡くなる直前に認知の症状が進んでしまったために
長女と母親が、父親の口座からキャッシュカードを利用して
資金を出金し、長女と母親の口座に移しました
その金額は総額で8000万です
その結果、相続開始時に父親の財産は
自宅不動産と預貯金1億2000万円でした
相続税の申告に当たって、税理士に相談したところ
直前に出金した8000万円も相続税の課税対象財産に
計上すべきという助言を頂きました
この8000万円は申告すべきでしょうか?
回答と解説
直前出金の8000万円は、税理士の助言通り
相続税の課税対象財産として計上する必要があります
相続税の申告に当たって
相続開始の日の残高だけが課税対象財産ではありません
今回のように、長女と母親が直前に出金した8000万円は
父親が長女や母親に贈与した資金移動ではありません
たとえ、今回と違って贈与が成立していた場合といえでも
生前贈与加算の対象となります
長女と母親の資金移動は、申告しなければ
税務調査によって必ず指摘されます
税務署は、被相続人(父親)の銀行口座を過去10年に
遡って資金移動を調べます
また、相続人の口座も同じく調査することができます
その過程で、今回のような資金移動は必ず
発見されます。
ですから、相続税の申告書には
現金として8000万円を計上する必要があります
相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
当事務所の強み
1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります
2.土日はもちろん365日対応します
3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です
4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます
6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します
7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
8.初回のご相談60分無料・着手金無料
9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています
10.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています
遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記
雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事
塗装工事・増改築など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる
業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
遺産分割協議が成立する前に土地を売却した場合に、所得税の申告は???
事例
Xさんが亡くなり、相続人はA・B・Cの3人です
Xの相続財産に占める不動産の比率は80%を
越えている為、X名義の預貯金だけでは納税資金が
不足しています。また、相続人のB・Cは不動産よりも
預貯金を相続したいと考えています。
そこで、AはX名義の不動産を全部売却してその売却代金を
法定割合で1/3づつ確定申告すればいいと考えています
しかし、BとCは売却代金を法定割合で分割することに
同意するかどうかわかりません
質問
上記のような場合、不動産譲渡所得の確定申告は売却代金の
1/3づつで申告すればいいですか?
回答
お尋ねの件について、一般的には不動産の相続登記割合
つまり1/3づつ売却代金を分配して、確定申告も
同じ比率で提出することになります
しかし、相続人が「土地の売却代金を一括して共同相続人の
1人に保管させて遺産分割の対象に含めることに
合意する」場合は、最終的な遺産分割協議書に記載の比率で
売却代金を分割して、相続税及び所得税の申告を行うことになります
【参考】最高裁昭和54年2月22日第一小法廷・・・
相続税の申告とご相談は、神戸・芦屋・西宮で
相続専門税理士として24年営業を続けている
私の事務所にお任せください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
生命保険金だけではなくて、生命保険契約にも相続税が課税!!!
相続税の申告に当たって
受取った生命保険金だけではなくて
生命保険契約にも相続税が課税されることを
ご存知ない方が多いので
解説します
事例
父親は、以下のような2つの生命保険契約を締結していました
1.契約者:父親 被保険者:父親 受取人:長男
2.契約者:父親 被保険者:孫 受取人:満期の場合は孫、孫死亡の場合は長男
このような生命保険契約を締結している父親の相続が開始しました
なお、2の生命保険については満期を迎えていません
このような状況で、相続税の課税関係はどうなるでしょうか?
解説
1の生命保険について、相続税の課税対象になることは問題ありません
しかし、2の生命保険について相続税の課税対象となることに
気づいていない場合が多くあります
2の生命保険は、父親が保険料を支払っていて
被保険者が孫であるため、父親が亡くなっても
保険金は支払われることはありません
ですから、生命保険の権利が相続税の課税対象となります。
また、この2の生命保険契約は1と違ってみなし相続財産ではありません
そのため、遺言書に記載がない限り孫がこの契約の権利を
相続できません。
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
孫の教育費をおじいちゃんが負担した場合の贈与税って???
孫の教育費をおじいちゃんが負担した場合の贈与税って???
少子高齢化により、子供や孫の教育費を祖父母が負担するケースは
増加傾向にあるようです
そこで、教育費の贈与について課税関係や限度額についての
お問い合わせが多くあります
教育資金贈与
一般的には、教育資金贈与という制度が知られています
詳細については、下記URLから国税庁のHPを
ご覧ください
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/201304/01.htm
この制度は、簡単に申し上げますと
金融機関に教育資金の為だけの特別な口座を
設けます。この口座から支払った教育費に関しては
非課税とする制度です。
相続税対策で、使いやすそうな制度ですが
実際に利用するとなると、様々な制限があって
この制度の利用を諦める方もいらっしゃるようです
実は、非課税ってご存知ですか???
実は、上記の教育資金贈与という制度を利用しなくても
教育費の贈与は、そもそも贈与税が課税されない
つまり、非課税ってご存知でしょうか?
教育資金の贈与は、非課税なんです
そもそも、民法では夫婦・直系血族等は相互に扶養する義務を
定めています
上記民法の定めに基づいて、贈与税では非課税財産を
以下のように定めています
「扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるためにした
贈与により取得した財産のうち通常必要と認められるもの」
この定めに基づき、おじいちゃんが孫の教育費を負担することに
対して贈与税は課税されないことが明らかです
それでは、「通常必要と認められるもの・・・」
の記載については、どこまでが非課税となるんでしょうか???
この点について、詳細を記載すると長くなるので
ここでは割愛させていただきますが
大原則として、教育資金の贈与は贈与税が課税されない
ということをご理解ください・・・ただし
通常必要と認められるものに限ります
相続税及び贈与税の対策と申告は
相続税専門の税理士にお任せください
神戸・芦屋・西宮のお客様をメインにしている
相続税専門税理士事務所は、こちらです
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
兵庫M&A・事業承継支援センターのHP
******************