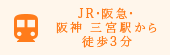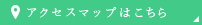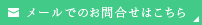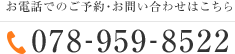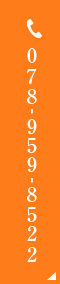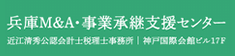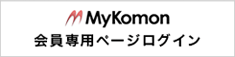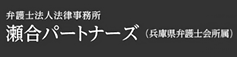代償分割と換価分割・・・どっちが節税できるのでしょうか?
事例紹介
Aさんは、今年の10月に亡くなるまで妻と死別後20年間一人暮らしでした
Aさんの法定相続人は長男と次男です
Aさんの相続財産は、わずかな現預金と自宅不動産だけでした
自宅は、Aさんが若いころに取得した戸建て住宅ですが
周辺の都市化にともなって評価額が上昇し、その結果
相続税の申告及び納税が必要となりました
Aさんの自宅の売却予定額は2億円ですが、相続財産に
現預金がほとんどないため、長男と次男は自宅を
売却した資金で納税することを決めました。
そこで、税理士と司法書士に相談したところ
「代償分割」と「換価分割」の二つの方法があると
アドバイスを受けました
代償分割と換価分割
土地の売却予定額が2億円程度ですが
長男と次男は6:4で分割することを考えています
『代償分割』・・・自宅を長男が相続し長男名義で登記後に
自宅を売却し長男は次男に40%である8000万円を
代償金として支払う旨の遺産分割協議書を作成します
『換価分割』・・・自宅を相続人代表ひとりあるいは
50%づつの比率で相続登記し、自宅を売却後に
代金を6:4に分割する旨の遺産分割協議書を
作成します
代償分割と換価分割の税務
今回のような事例で、不動産を売却しなければ
代償金の資金調達ができない場合、自宅の譲渡所得に伴う
所得税及び住民税は、すべて長男が負担することになり
税引き後の手取金額から代償金の8000万円を
支払うことになります
一方で、換価分割の場合は換金処分後の
税引き後手取額を分割対象とするので
譲渡所得に伴う所得税及び住民税は単独の負担ではありません
今回、不動産をいったん50%づつの相続登記を行っていますが
これは、不動産を譲渡するために便宜的に行っているだけで
手取金額の分割時は、分割協議書通りに6:4で
分割することができます
さらに、換価分割を前提とする場合
実務的には、相続人代表の名義のみで登記を行うことの
方が多いです。登記手続きのみならず売却手続きも
手間がかなり省けるからです。この場合も、上記と同様に
登記は1名ですが、売却代金を6:4で分割することになりますし
税務上も問題ありません
相続税対策のご相談や相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです
1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります
2.土日はもちろん365日対応します
3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です
4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます
6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します
7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
8.初回のご相談60分無料・着手金無料
9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています
10.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています
遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記
雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事
塗装工事・増改築など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる
業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計1000件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
住宅取得資金贈与を利用したために、相続税の申告で失敗しました
事例
母が亡き後、父は実家で一人暮らしをしていました
実家は、100坪の面積で芦屋の閑静な住宅街にありました
父親は、会社を経営していましたが75歳で兄(長男)に事業承継して
引退しました。私(長女)は、会社の株式を相続しないかわりに
実家を相続することが家族間の話し合いで決まっていました
父親が亡くなる数年前に、住宅取得資金贈与の制度を利用して
父親から資金贈与を受けつつ、不足額は夫がローンを組んで
自宅を購入しました。・・・
問題点
父の住む実家は、路線価評価が非常に高く
私が相続することになっていました
小規模宅地の特例という制度があるのですが
税理士から、適用できないと言われました
小規模宅地の特例を適用できる相続人の条件は
1.配偶者
2.同居親族
3.家なき子
と決まっているそうです
私は、住宅ローン控除を利用して夫と共有名義の住宅を
購入したために、上記1.2.3のどれにも該当することなく
小規模宅地の特例を適用できないままで
実家を相続することになりました
解決策
自宅を購入する前に、
相続税に詳しい税理士さんに相談すべきだったと
反省しています
相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
近江清秀公認会計士税理士事務所の強みは、以下の通りです
1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります
2.土日はもちろん365日対応します
3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です
4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます
6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します
7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
8.初回のご相談60分無料・着手金無料
9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています
10.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています
遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記
雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事
塗装工事・増改築など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる
業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計100件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
親族間でも借地権が発生します。
事例
Aさんが所有する遊休地に、長男Bさんが自宅を建築予定です
Bさんは、Aさんに地代を支払うつもりなのですが
Aさんは、地代をもらうと確定申告が必要になって
煩わしいので地代はいらないと考えてます
相続税の節税対策としては、Bさんは地代を支払うほうが
いいのでしょうか?
回答と解説
Bさんが、地代を支払うことにより
Bさんに税務上の借地権が発生します
その結果、Aさん所有の遊休地の税務上の評価額が下がるので
相続税対策としては有利になる場合があります
ただし、相続税対策として有利な結果となるために
考慮すべきポイントが2つあります
1.地代の金額をいくらで設定するのか、という論点です
地代は、高すぎても安すぎても税務上の借地権は0円となってしまいます
今回の場合、民法上の借地権は発生しますが税務上の借地権は
地代の金額次第ということです
2.借地権が最大に発生する地代を設定して毎月借地権を
支払う場合、地主さんの所有する土地の評価額は下がることになりますが
その一方で、金融財産は増えることになります
長期的に賃貸借契約が継続すると、土地の評価額の減額と
金融財産の増額が相殺されることになります
1,2から親族間で土地を賃貸借する場合には
地代を支払うかどうか、支払う場合は金額をいくらに設定するのか
について、慎重に検討する必要があります
相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
当事務所の強み
1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります
2.土日はもちろん365日対応します
3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です
4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます
6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します
7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
8.初回のご相談60分無料・着手金無料
9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています
10.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています
遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記
雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事
塗装工事・増改築など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる
業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
相続開始から4カ月経過していますが、準確定申告はどうすればいいですか?
事例
今年の5月に父親が亡くなり
相続税の申告が必要なのですが
その前に、所得税の準確定申告が必要です
申告期限が迫っているのですが、まだ必要な
資料を集めていません。どうすればいいでしょうか?
父親の所得は、公的年金と上場企業株式の配当金がわずかに
あるだけです。直近数年の父親の確定申告書を
確認すると、毎年還付申告だったようです
回答
準確定申告の申告期限は、相続開始の日から4カ月です
しかし、還付の場合4カ月経過後の申告であっても
問題ありません。
解説
今回のような準確定申告の場合揃えるべき必要な資料は
・公的年金の準確定申告書
・介護保険の支払金額の証明書
・後期高齢保険の支払金額の証明書
・配当金の支払通知書
です
なお、相続人が複数人で準確定申告の還付税金を
相続人間で分割せずに、ひとりの相続人が
受取る場合は、準確定申告書に付表を添付するだけでなく
委任状も添付する必要があります

相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
当事務所の強み
1.三宮駅から徒歩数分の神戸国際会館17階に事務所があります
2.土日はもちろん365日対応します
3.相続税の申告実績は過去24年間で約1000件です
4.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
5.すべての案件のお客様と所長が直接対応させていただきます
6.ZOOMを活用して日本全国の案件に対応します
7.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
8.初回のご相談60分無料・着手金無料
9.明石・神戸・芦屋・西宮の相続案件を得意としています
10.信頼できる多くの職人さんたちと連携しています
遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記
雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事
塗装工事・増改築など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる
業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
http://www.不動産賃貸税理士.com/
******************
遺産分割が成立しない場合の相続税の納税方法
【事例】
先日亡くなった父親の遺産は
現預金が1億数千万円と、不動産が自宅及び月極駐車場でした
相続人は、私と姉の2人ですが遺産分割について相続税の申告期限までに
まとまる見込みがありません
いくつかの分割パターン案に基づいて、それぞれのパターンの場合の
相続税額を税理士さんに試算してもらっています。
幸い、相続財産の現預金が1億数千万円あるため
分割協議さえ成立すれば納税資金に困ることはないのですが
私の固有の財産だけでは、納税資金は足りません
相続税の申告期限が迫っていますが、これからどうすればいいでしょうか?
【回答と解説】
結論から申し上げますと
ひとまず、相続税額に相当する金額だけ
預金の口座を等分に分割して納税します。
それだけです
全体の遺産分割協議が成立するのを待っていたのでは
納税資金が不足する事例はいくらでもあります
遺産分割が本人同士だけで話し合っているのか
双方に弁護士さんが関与しているのか、どちらであっても
納税期限が迫っているのであれば、全体の遺産分割協議に
拘る必要はありません。
最悪の場合、遺産分割協議書が
なくても法定相続人全員が実印を押印すれば銀行口座を
分けることはできます
つまり、全体の遺産分割ができない場合でも
相続財産の預金口座を納税資金に充当することについて
相続人全員が同意すればいいのです
例えば、相続人2人の相続税額総額が1500万円で
相続財産の中に残高1800万円の預金口座があった場合
その銀行の口座残高を50%づつに分けて、それぞれ
相続人の銀行口座に振込む手続き書類に実印を
押印すればいいのです
全体の遺産分割協議を成立させることにこだわって
納税資金の確保のタイミングを逸してしまい
納税期限に納税できない場合、後日延滞税が課税されることになります
遺産分割協議が、なかなか成立しないと見込まれる場合
まず、納税資金の確保のために銀行口座の分割だけでも
成立させましょう。

相続税の申告は、経験と知識が豊富な
専門の税理士に依頼する必要があります
当事務所の強み
1.すべての案件のお客様との面談は所長自らが担当します
2.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
3.相続税の申告実績は20年間で800件以上です
4.相続税の節税相談は20年間で2000件以上です
5.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
6.土日はもちろん祝日、お盆、年末年始も対応します
7.相続した不動産について、
遺品整理、空き家の大掃除、分筆の為の測量、名義変更登記
雨漏り・屋根修理、外構工事、電気工事、水回りの工事、内装工事
塗装工事など、不動産に関するお困りごとについて信頼できる
業者さんや職人さんをご紹介できます。遠慮なくお尋ねください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
居住用不動産の贈与をあった年に配偶者が死亡した場合の税金は?
事例
Aさんは婚姻関係が40年以上になるので夫であるBさんから
自宅の土地及び家屋(評価額1800万円)の贈与を受けました
しかし、Bさんはその直後に急死してしまったのです
さて、このよう場合相続税の申告と贈与税の申告は
どうなるのでしょうか?
回答
相続税は、課税対象外
贈与税は、申告して無税
となります
解説
資産の贈与があっても、相続開始の7年前の贈与財産については
相続税の課税価格に算入されてしまいます
しかし、その贈与財産が配偶者控除の適用を受けた居住用財産
である場合は、その特定贈与財産の評価額までは受贈配偶者の
相続税の課税価格に加算しないこととされています
(相続税法19条)
その一方で、生前贈与の加算対象とならない上記特定贈与財産については
その贈与が贈与した配偶者の相続開始の年に行われたものであったとしても
非課税財産に該当しないため、贈与税の申告が必要となります
この事例では、住宅の評価額が2000万円未満ですから
贈与税の申告をしても贈与税額は0円となります
神戸・芦屋・西宮エリアで相続税対策及び
相続税申告業務は、是非お任せください
当事務所の強み
1.すべての案件のお客様との面談は所長自らが担当します
2.税務調査を受ける確率が2%程度という驚異的な低さが自慢です
3.相続税の申告実績は20年間で800件以上です
4.相続税の節税相談は20年間で2000件以上です
5.弁護士・司法書士・土地家屋調査士と業務連携しています
6.土日はもちろん祝日、お盆、年末年始も対応します
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
遺産分割協議が成立する前に土地を売却した場合に、所得税の申告は???
事例
Xさんが亡くなり、相続人はA・B・Cの3人です
Xの相続財産に占める不動産の比率は80%を
越えている為、X名義の預貯金だけでは納税資金が
不足しています。また、相続人のB・Cは不動産よりも
預貯金を相続したいと考えています。
そこで、AはX名義の不動産を全部売却してその売却代金を
法定割合で1/3づつ確定申告すればいいと考えています
しかし、BとCは売却代金を法定割合で分割することに
同意するかどうかわかりません
質問
上記のような場合、不動産譲渡所得の確定申告は売却代金の
1/3づつで申告すればいいですか?
回答
お尋ねの件について、一般的には不動産の相続登記割合
つまり1/3づつ売却代金を分配して、確定申告も
同じ比率で提出することになります
しかし、相続人が「土地の売却代金を一括して共同相続人の
1人に保管させて遺産分割の対象に含めることに
合意する」場合は、最終的な遺産分割協議書に記載の比率で
売却代金を分割して、相続税及び所得税の申告を行うことになります
【参考】最高裁昭和54年2月22日第一小法廷・・・
相続税の申告とご相談は、神戸・芦屋・西宮で
相続専門税理士として24年営業を続けている
私の事務所にお任せください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
古い木造アパートを相続したんですが・・・交換ってできるんですか?
事例
私は、親から古い木造アパートを相続しました。
相続から5年経過しましたが、建物劣化が激しく建て替えるか
売却するか検討していました。
しかし、不動産業者の担当者から「隣の街の月極駐車場と交換して
その土地で新しく賃貸住宅を建設することができる」と
言われました。そんな都合のいい話は本当に実現するのでしょうか?
回答
要件を満たせば、税務上の問題をクリアできます
解説
いわゆる交換の特例を適用するための要件は以下の通りです
1.交換譲渡資産と交換取得資産はいずれもこ定子さんであること
2.交換譲渡資産を1年以上所有していたこと
3.交換取得資産は相手方が1年以上所有していたこと
4.交換譲渡資産と交換取得資産は同一種類の資産であること
5.交換後は、交換取得資産を交換譲渡資産の交換直前の用途と
同一の用途に供すること
6.交換譲渡資産と交換取得資産の時価の差額が、これらの時価のうち
高い金額の20%以下であること
これらの要件のうち、今回論点となるのは5番の要件です
交換譲渡資産は木造賃貸アパートの敷地で
交換取得資産は月極駐車場の土地です
単純に、これだけでは同一用途とならないため
交換の要件は満たしません
しかし、今回の交換取得資産である駐車場の立地が住宅地であり
既存の構築物を取壊したり造成工事をすることなく
いつでも建物を建設が可能な土地であれば宅地と同様に
取り扱うことができると考えられます
相続税の申告業務は、神戸・芦屋・西宮で
相続専門税理士として24年営業を続けている
私の事務所にお任せください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************
換価分割の留意点 3月10日の続き
このHPで換価分割の概要については3月10日に
解説しましたが、今日は前回書ききれなかった留意点を
記載します
事例
例えば、先祖代々の土地に父親Aさんが住んでいました
Aさんの配偶者は以前に亡くなっていましたが、Aさんの長女Xさんは
同居していました。またAさんにはXさん以外に長男Yさんと次男Zさんの
相続人がいます。
Aさんの遺産は、AさんとXさんが住んでいた自宅の不動産100坪(評価9000万)
と預貯金1億2000万です。遺産分割に当たっては兄弟で喧嘩はしていませんが
いろんなパターンを考えているようです
兄弟全員が、自宅をいずれ売却することについて賛成しています
そこで、分割パターン別に留意点を検討することになりました
検討
留意点1:XさんはAさんと同居していたので小規模宅地の特例が適用できます
小規模宅地の特例のメリットを最大限活かすためにはXさんが単独で
自宅不動産を相続する必要があります。しかしその場合、相続割合が
法定割合と大きく乖離するという問題があります
留意点2:留意点1の論点を解消するために、自宅不動産を換価分割する場合
法定分割となります。しかし、小規模宅地の特例のメリットを1/3しか
活かすことができません。今回の相続税ではXさんの単独相続と法定割合の相続では
3兄弟の相続税総額に700万円の差額が発生します。これは大きな問題です
留意点3:留意点2の分割パターンは、小規模宅地の特例のメリットが1/3となり
なおかつ相続税も700万円増加しますが、3兄弟平等というメリットがあります
これが換価分割の最大のメリットです
しかし、この方法も一つ問題があります。換価分割の為に自宅を売却した際の
所得税の金額について、XさんとYZさんとでは大きな差額が発生します
つまり、Xさんは実家でAさんと同居していたので譲渡所得税の計算にあたって
●居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除の特例と
●長期譲渡所得に軽減税率の特例を適用できるのです
せっかく仲のいい兄弟が遺産分割を平等にしても、譲渡所得税で大きく
差額が発生します。
このように、換価分割を実施する際には様々な論点が発生します
税理士は、分割案のパターン別に税額計算を行うことはできます
相続税の申告業務は、神戸・芦屋・西宮で
相続専門税理士として24年営業を続けている
私の事務所にお任せください
******************
近江清秀公認会計士税理士事務所
651-0087神戸市中央区御幸通8-1-6
神戸国際会館17階
(Tel)078-959-8522
(Fax)078-959-8533
オフィシャルHP
https://www.marlconsulting2.com/
AI搭載クラウドシステムfreeeの導入兵庫県第1位のHP
累計800件以上の相続税申告実績!相続税専門税理士のHP
不動産賃貸専門税理士のHP
******************