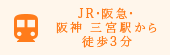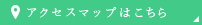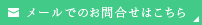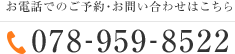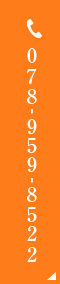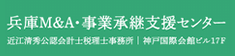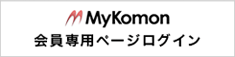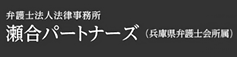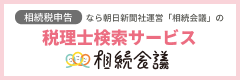【相続税質疑応答編-9 死亡退職金の支給対象者が未定の場合の課税関係は?】
<事例>
株式会社甲の取締役Xがプライベートの旅行中の事故でこの度亡くなりました。
甲社は、退職金規定に基づいて、死亡退職金5000万円と死亡弔慰金1000万円
の支給を決定しました。
株式会社甲の退職金規定では、退職金の支給対象者を定めていないので
通常は、「ご遺族ご一同様」を対象に支給されます。
この場合の、課税関係はどうなりますか?
なお、取締役甲の月額役員給与は100万円で、甲の法定相続人は
配偶者Yと長男Zの3名です。
<解説>
今回の事例には、論点が2つあります。
1.退職金と弔慰金を支給された場合の相続税法の取扱
2.支給対象者が未定の場合の取扱
では、1つの論点から説明します。
死亡弔慰金については、相続税法基本通達3-20で以下のとおり定めています
(相続税基本通達3-20 一部省略)
『被相続人の死亡により相続人その他の者が受ける弔慰金等」については、、
次に掲げる金額を弔慰金等に相当する金額として取り扱い、当該金額を超える
部分の金額があるときは、その超える部分に相当する金額は退職手当金等に
該当するものとして取り扱うものとする。
1.被相続人の死亡が業務上の死亡であるときは、その雇用主等から
受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の
普通給与の3年分に相当する金額
2.被相続人の死亡が業務上の死亡でないときは、その雇用主等から
受ける弔慰金等のうち、当該被相続人の死亡当時における賞与以外の
普通給与の半年分に相当する金額』
今回の事例では、事故死なので上記2に該当します。その場合
会社の支給する弔慰金1000万円のうち600万円を上回る400万円が
死亡退職金として取り扱われます。その結果、相続税の対象となる
死亡退職金は、本来の退職金5000万円に400万円を加算して5400万円と
なります。
次に、論点2の説明をします。
会社の退職金規定に死亡退職金の支給対象者が明示されていない場合について
相続税基本通達3-25に、退職金の支給を受けたものを定めています
(相続税基本通達3-25 一部省略)
『被相続人に支給されるべきであった退職手当金等の支給を受けた者とは、
次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に掲げる者をいうものとする。
1.退職給与規程等の定めによりその支給を受ける者が具体的に
定められている場合当該退職給与規程等により支給を受けることとなる者
2.退職給与規程等により支給を受ける者が具体的に定められていない場合
又は当該被相続人が退職給与規程等の適用を受けない者である場合
イ 相続税の申告書を提出する時又は更正若しくは決定をする時までに
当該被相続人に係る退職手当金等を現実に取得した者があるときは、その取得した者
ロ 相続人全員の協議により当該被相続人に係る退職手当金等の支給を受ける者
を定めたときは、その定められた者
ハ イ及びロ以外のとき その被相続人に係る相続人の全員。この場合には、
各相続人は、当該被相続人に係る退職手当金等を各人均等に取得したものとして
取り扱うものとする。』
上記の定めに基づくと、今回の事例では2-ハに該当します。
そのため、X取締役の妻Yと長男Zは5,400万円の死亡退職金を
2700万円づつ受取ったとして相続税の計算を行うことになります。
ただし、死亡退職金については法定相続人1人につき500万円の非課税金額が
定められていますので、Y・Zともに2200万円づつが相続税の課税
対象金額となります。
この記事以外にも、下記URLのマイベストプロ神戸に私のコラムの
書込みをしていますのでご覧ください
http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/column/